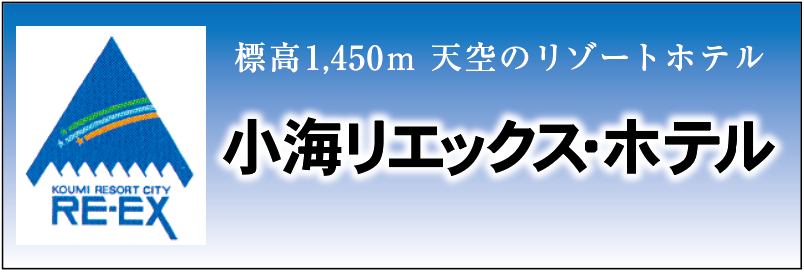会田淳さん(千葉県出身)会田芳実さん(茨城県出身)
宅配会社に勤めていた淳さんは、週末になると東京の自宅から茨城県にある就農準備校へ車で通っていた。さらに、二週間ほど原村にある八ヶ岳中央農業実践大学で学んだ。
就農してからも、大分県で循環農法を実践し、数々の著書を出版していた赤峰勝人さんの元へ通った。短期間で集中して行う座学や現場作業の濃密な時間は何よりも農業の知識と技術を深めてくれた。泊まり込みや合宿が好きで、飲み会の時は最後までいる性格はたくさんの人との関わりを通して自分への糧としている。
芳実さんは、1970年代から始まった、有機農業の生産者と消費者が直接繋がる仕組み「提携」の消費者だった家で育ち、子どもの頃に援農として連れて行ってもらった農業の体験がとても楽しく感じたことをきっかけに農業の道を目指すようになった。一人農業で栽培から販売まで行い、直接お客様のところまで配送していた。
–就農準備校:全国を対象に民間の農業研修機関を活用して、就農を志している人や就農を 始めたばかりの人に技術や経営を教えてくれる国の制度
“わっか農園” の続きを読む